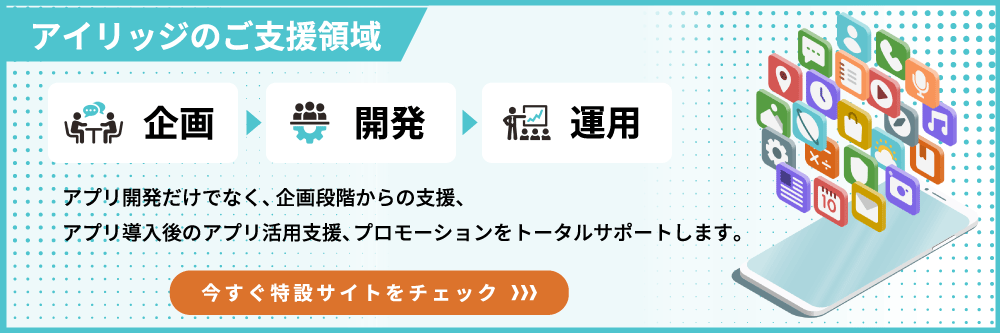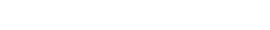アプリ開発の要件定義とは?テンプレ・サンプル付きで必要項目・進め方をわかりやすく解説

自社アプリを開発するにあたり、「要件定義」の設定が必要になります。
要件定義とは、アプリ開発に必要な要件や機能、制約条件などを定めることです。
もし要件定義をしないままアプリ開発を進めてしまうと、工数が肥大してコストが増加したり、やり直しが発生して納期が遅延したりするなどのリスクを伴います。
このようなリスクを回避するためにも、アプリ開発の要件定義について理解することが大切です。
そこで本記事では、アプリ開発の要件定義について、目的や含めるべき内容とテンプレ項目、失敗しない進め方、作成時の重要なポイントなどをまとめて紹介します。
要件定義書を外注すべきケースなども解説しているので、アプリ開発を検討している方はぜひ参考にしてください。
アプリ開発の要件定義とは?

そもそも要件定義とは、設計や実装作業を行う前の工程であり、開発目的を明確にするための作業・工程です。
アプリ開発の要件定義は何を目的に行われるのか、また行わないとどのような失敗につながりやすいのか解説します。
要件定義の目的
アプリ開発で要件定義を行う目的に、発注者側と開発者側で起きやすい認識のズレをなくすことが挙げられます。
いくら発注者側が「こんなアプリをリリースしたい」と思っていても、開発者側との間に認識のズレが生じていると想定とは違うアプリが完成する可能性が高いです。
要件定義では、アプリを開発する目的や必要な機能・性能などを定めているため、開発側はその内容に沿ってアプリを開発できるようになります。
また、要件定義を作成することでアプリの仕様が確定し、そこからスムーズに設計やコーディングなどに移行できます。
しかも工数なども決まるため、アプリ開発にかかる大まかな費用を算出することも可能です。
このように、要件定義を作成することでアプリ開発はスムーズに進行し、質の高いアプリをリリースできるようになるでしょう。
要件定義を行わないと起こる失敗事例
アプリ開発において要件定義を行わなかった場合、以下のような失敗が起きる可能性が高まります。
例えば、工数の肥大が挙げられます。
当初予定していた工数があったとしても、要件定義を行わなかったことで機能の追加や修正により、工数が増えてしまう可能性があります。
工数が増えるということは、それだけ人件費などのコストも増加し、予算オーバーにつながるリスクもあるでしょう。
また、要件定義を行わないまま開発を進めていった結果、発注者側と開発者側で認識のズレがあったことが後から発覚し、大規模な修正またはほぼ最初から作り直しになるケースも考えられます。
そうなると一からコストをかける必要があり、最悪の場合プロジェクトそのものが頓挫する可能性もあるのです。
理想的なアプリを納期までに完成させ、予定通りリリースするためにも、要件定義は必要となります。
要件定義書に含めるべき内容とテンプレ項目一覧

要件定義書に含める項目に決まりなどはありませんが、基本的には以下の項目は含めたほうが認識のズレを減らし、スムーズな開発につながります。
- 企画概要/背景
- 業務要件
- 機能要件
- 非機能要件
- UI/UX要件
- 開発方式
- 想定工数・予算の前提条件
① 企画概要/背景
企画概要では、主にアプリ開発の目的や背景などを示します。
目的や背景はより具体的に記載したほうが、開発者側もその意図を理解した上で開発に移行できます。
背景の具体性を増すには、数字や実例を組み入れて説明するようにしましょう。
さらに、アプリ開発の目的を記載する際にはアプリ開発によって何を実現したいのか、具体的な数値目標なども明記します。
また、競合分析を活用し、要件定義の概要に組み込むのもおすすめです。
他社が提供するアプリやサービスに対して不満を抱くユーザーもいますが、この不満点を洗い出し、解消できる機能を自社のアプリに盛り込めば他社との差別化にもつながります。
さらにアプリ開発の方向性がより明確になり、顧客ニーズを的確に捉えた状態で機能要件なども設定できるでしょう。
こういったメリットから、要件定義を作成する前に競合分析を行い、企画概要にその内容を取り入れてみてください。
アプリ開発の企画書作成についてより詳しく知りたい方は以下の記事も参考にしてください。
② 業務要件
業務要件とは、アプリごとにシステム化する業務と、実際にシステム化するための操作手順やフローを明確にした要件を指します。
例えば、業務内容や業務フロー図、組織図、規模の定義、スケジュール、指標、業務要件の対象となる範囲などです。
業務要件を含めていないと、業務全体の流れがわかりづらくなり、スケジュールも曖昧なものになる可能性があります。
また、運用体制などを明確にし、誰が担当者になるのかも業務要件で記載することになります。
業務要件の中で特に重要となるのが「業務フロー図」です。
業務フロー図は誰が・いつ・どのような作業・どのような流れで行うのかを視覚的に示し、関係者全員がどのように業務を進めていけばいいか理解できるようにします。
また、業務フロー図の中に時間軸を設け、各ステップの所要期間や発生するタイミングなども記載する場合もあります。
③ 機能要件
機能要件とは、アプリにどのような機能を設けるのかを記載する項目です。
要件定義書の大部分を占める項目で、実装する機能はここで漏れなく洗い出すことが重要となります。
実装する機能の一覧だけでなく、各機能の画面イメージや情報・データ項目、外部インターフェースなども機能要件に記載します。
機能はただ実装したい機能を洗い出すだけでなく、どのように利用されることを目的とする機能なのか、その情報はどのように扱われるのかまで具体的に定義することが大切です。
可能であれば活用例やユーザーが使用する流れなども記載されていると、より明確でわかりやすい要件定義書になります。
④ 非機能要件
非機能要件とは、アプリの機能以外で求めることを指します。
機能要件ではアプリの具体的な機能を洗い出しましたが、非機能要件はそれ以外のすべてになります。
例えばアプリのセキュリティ(アクセス制限、不正検知など)やパフォーマンス(処理性能・拡張性など)、API連携などは非機能要件の中で示します。
非機能要件は基本的に発注者側から具体的な希望が上がることは少ないです。
そのため、開発者側が非機能要件をまとめ、発注者側に提案するケースが多く見られます。
業務要件・機能要件に当てはまらない要件は、ほとんどが非機能要件に含まれることになるため、こちらも抜けがないように注意してください。
⑤ UI/UX要件
UI/UX要件は、UI(ユーザーインターフェース)とUX(ユーザーエクスペリエンス)で必要な要件を定める項目です。
UIはアプリを操作する際のインターフェースのデザインなどを指し、要件定義書ではユーザーが操作する画面をイメージし、カラーやフォント、ボタンの配置などを決めていきます。
UXはユーザーがアプリを通じて得られる体験という意味があり、要件定義書では主にナビゲーションやタスクフロー、フィードバックなどの仕組みを設計し、まとめることが多いです。
画面構成に加え、導線やワイヤーフレームなどもUI/UX要件で決めます。
ワイヤーフレームとは、線と枠だけで構成されたアプリのプロトタイプです。
完成イメージを共有できるだけでなく、開発前に画面数やデザインの見通しも立てられるため、コスト面を精査することもできます。
アプリのUIについてより詳しく知りたい方は以下の記事も参考にしてみてください。
⑥ 開発方式
アプリをどのような開発方式で構築するのかも要件定義書にまとめる必要があります。
開発方式の種類には、例えば「フルスクラッチ」と「パッケージ」があります。
フルスクラッチはアプリを一から構築する開発方式であり、発注者側の要求を盛り込んだアプリを開発できます。
ただし、一から構築する必要があるため、制作期間とコストが多くかかってしまいます。
パッケージは元々開発されている機能を活用し、アプリ開発に取り入れる方式です。
既存の機能を活用していることから、フルスクラッチに比べて開発工程やコストを抑えやすいです。
ただし、既存の機能しか基本的に盛り込めないので、フルスクラッチに比べると自由度は劣ってしまいます。
開発方式によってかかるコストや期間などが異なることから、開発方式も要件定義書に示しておくことが大切です。
⑦ 想定工数・予算の前提条件
要件定義書には想定工数と予算の前提条件も記載し、発注者側と開発者側で共有することが大切です。
工数や予算は開発方式や機能の規模、セキュリティ要件などによって異なることから、上記の要件定義をもとにプロジェクト全体の工数と予算を割り出していきます。
要件定義の内容が事細かに決められていれば、それだけ想定工数や予算などの見積もりでギャップが起きにくく、より正確なスケジュールを組むことも可能です。
見積もりに関しては要件定義書にまとめて終わりではなく、開発途中で仕様が変わったり機能を追加してほしいと要望があったりした場合に、適宜見直しが必要です。
要件定義書テンプレートの種類

要件定義書には決まったフォーマットは存在せず、テンプレートなどはPDFやExcel、PowerPoint、Wordなどで作られることが多いです。
これらの出力形式は目的や共有したい相手、開発フェーズなどによって適切な形式が異なります。
ここで、要件定義書テンプレートの種類とその特徴について解説します。
PDF:完成形を共有する用途に最適
PDF形式で出力した要件定義書は、内容が一通り確定した後の共有・保存に最適です。
レイアウトが崩れにくく、閲覧環境も問わないため、社外の開発会社や関係者に渡す正式な資料としてもよく活用されています。
また、編集できない形式になるため、合意済みの内容という認識をそろえることも可能です。
他にもExcelやPowerPoint、Wordなど複数のソフトを活用した場合、PDFにまとめることで表示するソフトを何度も切り替える必要はありません。
ただし、修正や差分管理はできないことから、作成途中のやり取りがある場合は別の形式を活用し、最終版をPDF化するのがおすすめです。
Excel:機能一覧や工数管理と相性が良い
Excelは、要件定義書の中でも機能一覧や画面一覧、非機能要件の整理などで活躍します。
行単位で機能を整理でき、優先度や対応の有無、想定工数、見積もりなどをまとめて管理でき、構造化された情報を扱うのに適しています。
発注者側と開発者側でやり取りをする際に、どこまで対象範囲になるのか、追加要件になるかなどが明確であり、仕様の抜け漏れなどを防ぐことも可能です。
手軽に導入でき、データ管理がしやすいのはExcelの大きなメリットと言えるでしょう。
ただし、Excelだけだとテキストでの背景説明や要件の意図などは伝わりにくくなってしまいます。
そのため、PowerPointやWordと組み合わせて使われる傾向にあります。
PowerPoint:社内共有・提案に使いやすい
PowerPointは、エンジニアではないすべての関係者へ説明するのに適した形式です。
テキストの挿入はもちろん、画面イメージや構成図などを視覚的に表現できるため、最終版のアプリがどのようなデザインになるのか想像しやすくなります。
特に経営層や他部署に説明する場合や、開発予算の承認を得る際には事細かに書かれた要件定義書よりも、要点をまとめたスライド形式のほうがわかりやすいです。
こうした理由から、社内共有や他部署などに提案する際は、PowerPoint形式が使いやすいでしょう。
一方で、要点をまとめることはできても、細かい仕様や例外条件まで網羅するとなると、テキストでいっぱいになり、見にくい資料になってしまいます。
要件定義の補足資料や説明資料としてPowerPointを活用するのがおすすめです。
Word:文章中心の仕様を残したい場合に便利
Word形式で作成する要件定義書は、業務要件や背景、前提条件など、文章量が多くなる要件を整理するのに役立つ形式です。
章立てや見出しなども整えやすく、しっかりと文章で「なぜこの機能が必要なのか」「どういった運用を想定しているのか」などを丁寧に文章で残せます。
ただし、Wordはあくまで文章作成に適した形式であり、複雑なレイアウトや画像・グラフを挿入しようとすると配置が不安定になる可能性があります。
また、機能一覧などの管理もしにくいため、Wordで要件定義書を作成する際はExcelなどと役割を分けて作成するのがおすすめです。
IPAサンプルとの違い
IPA(情報処理推進機構)では要件定義書のサンプルを公開しており、こちらを活用することも可能です。
IPAの要件定義書のサンプルは網羅性と厳密性を重視した構成になっています。
ただし、一般企業のアプリ開発にそのまま使ってしまうと、以下のデメリットを受ける可能性があるので注意が必要です。
- 項目が多すぎて運用が難しい
- 書くこと自体が目的化するリスクがある
- 高度な知識が前提で、初心者には難しい
- 国家プロジェクトや大規模案件向けの構成
- 現場実務との乖離が発生する可能性がある
そのため、IPAサンプルを活用する際には、中小企業の実務に落とし込んでカスタマイズをすることが大切です。
例えば、自社にとって不要な項目は使わなかったり、すべて文章化するよりも一覧や図などで代替できる部分を探したりするなどです。
要件定義書のフォーマットの種類
要件定義書のフォーマットにはさまざまなものがありますが、ここでは代表的な3つを紹介します。
- 機能仕様書:アプリ開発で広く使われているフォーマットで、主にアプリの機能(アプリで何ができるか)をまとめるのに使われる。わかりやすく丁寧に内容を記載することが重要。
- ユーザーストーリー:ユーザー視点で要件をまとめるフォーマットで、UX(アプリを通じてユーザーにどのような体験を提供するか)を定義するのに使われる。ユーザーの行動を忘れずに記載することが重要。
- スケッチ・ワイヤーフレーム:アプリの視覚要素をまとめるフォーマットで、UI(アプリの見た目)を定義するのに使われる。アプリの全体像が見えやすくなるのがメリット。
要件定義の際にはどれか1つのフォーマットに絞る必要はなく、開発するアプリの内容によって臨機応変にさまざまなフォーマットを使い分ける必要があります。
また、複数のフォーマットを組み合わせて要件定義書を作成することで、より正確に要件を整理することが可能になります。
アプリ開発の要件定義:失敗しない進め方

実際にアプリ開発の要件定義を行う場合、どのような進め方を採用すると失敗しにくくなるのでしょうか?
ここで、要件定義の失敗しない進め方を解説します。
ステップ1 キックオフ&ヒアリング
まずは新しいアプリ開発のプロジェクトの始まりに、すべての関係者の足並みをそろえるためにキックオフミーティングが行われます。
キックオフミーティングではプロジェクトの目的や方向性を明確にし、関係者全員に共有することが可能です。
また、プロジェクトの範囲やチーム内における役割と責任者を明確にしておきます。
それから要件定義書の作成に向けて、ヒアリングが実施されます。
ヒアリングでは現在の課題やアプリに盛り込みたい機能などを明確化し、要求項目に漏れがないか確認します。
さらに、開発者側はこれらの要件に対して、非機能要件における部分などを提案する場合もあります。
ステップ2 画面遷移図・ワイヤーフレームの作成
キックオフミーティングやヒアリングで出た要求内容をまとめたら、画面遷移図とワイヤーフレームを作成します。
画面遷移図とは、アプリの各画面がそれぞれどのように関係し、どう遷移していくかを視覚的に整理した図です。
画面遷移図を作成することで必要な画面を洗い出すことができ、不足や重複をなくせます。
また、アプリの全体像が把握しやすかったり、UXの複雑化を最小限に抑えられたりするなど、メリットも多いです。
ワイヤーフレームも画面遷移図と同様に、アプリの全体像を把握するのに役立ちますが、基本的にはUIデザインを定義するのに活躍します。
アプリ向けのワイヤーフレームについてより詳しく知りたい方は以下の記事も参考にしてみてください。
ステップ3 機能要件の優先度付け
発注者側からさまざまな要求が来る場合もありますが、1つのアプリに収まりきれない場合もあります。
限られた期間とリソースの中でアプリ開発を行う場合、機能要件に優先度を付けることも大切です。
機能要件の優先度を決める際に活用されるのが、「MoSCoW分析」と呼ばれる分析手法です。
MoSCoW分析では各要件を以下4つのカテゴリに分類し、優先順位を付けていきます。
・Must(必須)
Mustのカテゴリには、開発するアプリに必要な要件が分類されます。
必須度は非常に高く、例えばこの要件を満たせないと開発プロジェクト自体が頓挫するほど、アプリの根幹を担う要件になります。
・Should(対応すべき)
Shouldには、要件を満たせないことでアプリ開発が中止になることはなくても、影響を受けてしまうステークホルダーやユーザーが多い要件が分類されます。
・Could(できれば対応したほうがいい)
Couldは、Shouldと同様に要件を満たせていなくてもアプリ開発は行われますが、ユーザーなどに影響する可能性があるものが分類されます。
Shouldとの違いは影響の程度だけで、稀に起きるエラー対応などはCouldに該当します。
・Won’t(対応しなくていい)
Won’tはこのアプリ開発に不要な要件や、今回のリリースまでに対応しなくても良い要件が分類されます。
ステップ4 開発方式の決定
次に開発方式を決定します。
開発方式は上記でも紹介したように、フルスクラッチまたはパッケージから選ぶことになりますが、さらにアプリの種類・形式についてもここで決めておきます。
形式にはネイティブアプリ・Webアプリ・ハイブリッドアプリの3種類があり、それぞれ特徴が異なります。
ネイティブアプリは、主にApp StoreやGoogle Playストアなどのストア経由でダウンロードできるアプリです。
特定のプラットフォーム専用に開発されていることから、スマホOSの機能を最大限活用できます。
Webアプリはブラウザ上で活用できるアプリです。
ストアを経由せずにリリースできるため手数料の支払いを回避できますが、ネットに接続した状態でないと動作しません。
ハイブリッドアプリは、ネイティブアプリとWebアプリを組み合わせて開発するアプリです。
マルチプラットフォームのため、どのOSでも機能し、WebViewを活用することでアプリ内からWebサイトを表示することもできます。
ステップ5 工数・費用の算出とスケジュール化
要件定義がまとまったら、その内容を踏まえて工数や費用を算出していきます。
最終的な開発工数と費用はプロジェクトの指針にもなることから、慎重に検討する必要があります。
見積もりを出した上で、どうしても予算内に収まらなかった場合には、優先順位の低い機能を中心に外していき、できる限り予算内に収めるケースが多いです。
工数や費用を算出したら、次に工数をスケジュールに落とし込んでいきます。
計画段階での見積もりが甘いと、スケジュールは大きく崩れる可能性があるため、実態に即したスケジュール設計を行うことが大切です。
アプリの開発費用については以下の記事でも解説しています。
要件定義書を作成する際の重要ポイント

最後に、要件定義を行う際の重要なポイントを4つご紹介します。
ポイント1 機能の優先順位付け
要件定義書を作成する際に、特に機能要件で優先順位を付けたほうが良いです。
すべての機能をまとめて盛り込んだ場合、工数が増えるだけでなく開発費用も大きく膨れ上がる可能性があります。
予算を大幅にオーバーした結果、アプリ開発のプロジェクト自体が頓挫する可能性もあるので注意が必要です。
また、優先度付けでMoSCoW分析を取り入れる際には、いくつか注意すべきポイントがあります。
例えば、同じ優先度の要件が揃っている場合、MoSCoW分析を行ってもあまり意味がありません。
また、MoSCoW分析を取り入れるタイミングによって優先順位が変動するケースもあることから、定期的に分析のし直しを行うことも考慮したほうが良いでしょう。
ポイント2 ユーザー操作を“実際の利用シーン”で設計する
要件定義書を作成する際に画面遷移図やワイヤーフレームなどもあわせて作成しますが、このときユーザーが操作する画面は、実際の利用シーンを想定して設計することが大切です。
例えばユーザーが実際にスマホを使って操作する際、使いやすくパッと見でわかりやすいレイアウト・デザインにすることが大切です。
実際の利用シーンを想定して設計する場合、アプリのターゲットユーザーを明確にすることも重要なポイントとなります。
ターゲットの属性によって操作しやすい・わかりやすいデザインなどが変わってきます。
アプリを使用するユーザーの性別や年代、住んでいる地域、職業などを明確にしておき、設計するようにしましょう。
ポイント3 UI/UXの一貫性を保つ
ユーザーに受け入れてもらいやすいアプリを開発するには、UI/UXへの配慮は必須と言えます。
しかし、単にUI/UXデザインを取り入れるだけでなく、アプリ内で一貫性を保つことも重要です。
アプリの一貫性とは、UI/UX全体でデザインに使用する要素・パターンを統一させることです。
一貫性のあるデザインを採用すると、ユーザーはこれまでの経験からアプリ内のさまざまな要素における動作を予測しやすくなり、より素早く目的を達成できるようになります。
短時間での目的達成によってユーザーの満足度も向上しやすいです。
UI/UXの一貫性を保つには、カラーパレットやアイコン、タイポグラフィ、言語スタイルなど、事前にデザインシステムを構築し、要件定義書にまとめておくのがおすすめです。
ポイント4 ステークホルダーとの“認識ズレ”を防ぐ工夫
要件定義書は、発注者や開発者、関係者と認識のズレをなくすことを目的に作成しますが、要件定義書を作成しても認識のズレが生じる可能性もゼロではありません。
例えば使用する言葉が曖昧で、受け取り方がそれぞれの立場によって異なっていたり、要件定義書のフォーマットがバラバラで同じ内容でも見え方が違ったり、コミュニケーションの頻度が低く「わかったつもり」が発生しているなどです。
こうした認識のズレを防ぐためにも、関係者全体で密なコミュニケーションを心がけることが大切です。
例えばヒアリングの際にわからないことがあれば質問し、疑問を解消しておくことで相互の理解を深められます。
また、単にコミュニケーションの回数を増やすだけでなく、丁寧な説明や質問しやすい雰囲気を作ることも重要です。
外注時の注意点については以下の記事でも解説しています。
アプリ開発会社が見る「良い要件定義書」の基準

アプリ開発会社にとって要件定義書は、設計・見積もり・開発判断のすべての起点となる重要な資料です。
内容が整理されていない要件定義書は、認識のズレや追加開発、スケジュール遅延の原因になりやすくなります。
ここでは、開発会社が「この要件定義書は良い」と判断する代表的な基準を紹介します。
粒度の均一性
良い要件定義書の大きな特徴は、記載されている情報の粒度が揃っていることです。
例えば、ある機能では画面構成や操作フローまで詳細に書かれている一方で、別の機能では「◯◯機能を実装する」とだけ書かれている場合、開発者側はどこまで作り込むべきか判断できません。
特に問題になりやすいのが、以下のような情報の偏りです。
- 機能要件はあるが、UI・画面遷移の情報がない
- 画面はあるが、裏側の処理や制約条件が書かれていない
すべてを同じ詳細度で書く必要はありませんが、「どの機能も、判断に必要な最低限の情報が揃っている」状態を意識することで、認識のズレを大きく減らすことができます。
前提条件と対象範囲(スコープ)が明確
開発会社が最も重視するポイントの1つが、どこまでが開発対象で、どこからが対象外なのかが明確に示されているかどうかです。
例えば、以下のように前提条件が曖昧だと、見積もりやスケジュールなども不安定になります。
- 管理画面は今回の開発範囲に含まれるのか
- 初期リリース時点で必要な機能はどこまでか
- 外部サービス連携や将来対応は含まれるのか
「書いていないから対象外」「想定していると思っていた」といった食い違いは、トラブルの原因になりやすいため、やること・やらないことを明文化することが、良い要件定義書の条件です。
判断に迷う余白がない状態
良い要件定義書は、開発会社が独自解釈をしなくても判断できる状態になっています。
仕様の曖昧さが残っていると、開発側は都度確認が必要になり、進行が遅れたり、認識ズレのまま実装が進んでしまったりする可能性があります。
- 「使いやすくする」「適切に表示する」といった抽象表現
- 条件分岐や例外処理が書かれていない仕様
- 仕様が複数の解釈に取れる表現
これらは、判断に迷う余白を生みやすいポイントです。
すべてを細かく決め切る必要はありませんが、「ここは開発会社に任せる」「ここは要件として固定する」という線引きを明確にすることで、スムーズで品質の高い開発につながります。
要件定義書を外注するべきケース

要件定義書は基本的に自社で対応することが多いですが、外注することも可能です。
要件定義書を外注したほうがいい場合とは、具体的にどのようなケースになるのか解説します。
社内にPM/ディレクション人材がいない
アプリ開発の上流工程にあたる要件定義は、基本的にプロジェクトマネージャー(PM)が中心となって進めていくケースが多いです。
PMはプロジェクトの計画や実行、監視、終了までを管理するのが主な役割であり、アプリやプロジェクト全体を把握・共有に必要な要件定義を作成します。
もし、社内にPMやアプリ開発のプロジェクトをディレクションできる人材がいない場合は、外注を検討しましょう。
専門の人材がいない状態で要件定義を作成しようとすると、要件定義でミスが発覚した場合に開発作業の遅れやコストの増加などが発生するリスクが高まります。
リリースできたとしても、ユーザーのニーズに合わないアプリになってしまう可能性も考慮すると、初めから外注に依頼したほうが良いと言えます。
システム連携が必要な場合
開発したいアプリにシステム連携が必要な場合も、外注を検討したほうが良いです。
例えば、店舗のPOSシステムとスマホアプリを連携させることで、顧客管理の効率化やリアルタイムで売上・在庫管理ができるようになります。
CRM(顧客関係管理)システムと連携させると、顧客情報がリアルタイムで管理できるようになり、一人ひとりのユーザーに対して適切な対応が取れるようになります。
また、API連携はアプリ間またはシステム間でデータや機能を連携でき、他社サービスの情報を使ってログインできたり、セキュリティレベルを高く保ったりすることも可能です。
このように、アプリとシステム連携によって利便性は高まりますが、プロセスは複雑なものになり、開発や運用にかかるコストも増加する可能性があります。
そのため、初めてアプリ開発・運用に取り組む場合には、要件定義書の作成を外注に依頼したほうが良いでしょう。
複数機能を同時に開発する場合
1つのアプリに対して複数の機能を盛り込みたい場合、開発工程では同時進行で進めるケースも少なくありません。
例えば実店舗でも使用するECアプリを開発したい場合、EC機能を備えるのはもちろん、実店舗で使える会員証機能や、クーポンを配布する機能などもあるとユーザーにとっては非常に利便性の高いアプリになります。
こうした複数の機能を盛り込みたくても、初めて要件定義書を作る場合には内容に漏れが生じてしまうかもしれません。
複数機能を搭載したい場合に漏れが出ないようにするために、外注がおすすめです。
アイリッジなら要件定義〜企画書・RFP作成まで一気通貫で支援可能

アプリ開発の失敗パターンで多いのが、 「要件定義だけ外部」「企画書やRFPは社内で」「開発は別会社」といった 分断された体制 によるズレです。
アイリッジでは、アプリ企画の上流工程から開発までを 5つのフェーズ に分け、以下のように一気通貫で伴走できる体制を整えています。
- フェーズ1:要件の整理(現状把握・ヒアリング)
- フェーズ2:現状分析(市場調査・ニーズ調査い)
- フェーズ3:UX戦略・企画策定(バリュー創出・コンセプト設計)
- フェーズ4:ユーザー体験デザイン(ユーザー体験・コミュニケーション設計)
- フェーズ5:アウトプット(企画書・提案依頼書(RFP)
まとめ

アプリ開発における要件定義書は、アプリ開発を滞りなく正確に進めるため、そしてプロジェクトの進捗管理をスムーズに行うために欠かせません。
発注者側と開発者側で認識にズレが生じないように気を付けながら、密なコミュニケーションを取りつつアプリ開発を進めていきましょう。
「初めてアプリ開発に取り組むが、どのように進めればいいかわからない」「アプリ企画を絶対に成功させたい」と考える人には、アイリッジの「アプリ企画/RFP作成支援」がおすすめです。
RFP(提案依頼書)は、外部の開発会社に対して開発依頼をするドキュメントを指します。
アイリッジではヒアリングから市場・ニーズ調査、UX戦略・企画策定、ユーザー体験・コミュニケーション設計、企画書/RFPの作成まで、一貫したサポートが可能です。
また、支援範囲は企画段階から開発、アプリ導入後の運用までトータルでのサポートにも対応しています。
アプリ開発で要件定義に自信がない場合や、総合的なサポートを受けたい場合には、ぜひアイリッジまでご相談ください。